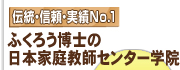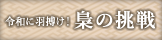開催500回を超える研修会
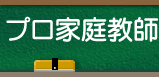 |
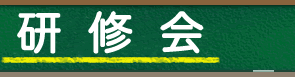 |
 |
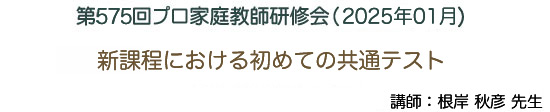 |
|
新学習指導要領の下での学習(以下、新課程とする)が、2022年4月から高校1年生に対して始まった。その高校1年生が3年生となり、2025年1月18日(土)、19日(日)の両日、新課程に対応する初めての共通テストが実施された。前回までの共通テストとは異なる部分もあるので、注目すべき点を報告する。 1.新学習指導要領と新共通テスト(1)新学習指導要領 2017年に改定された新学習指導要領では、 [1] 実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技能」
社会に出てからも学校で学んだことを生かせるよう、これら3つの力をバランスよく育むことを目指す、としている。 [2] その知識・技能をどう使うかという、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力など」 [3] 学んだことを社会や人生に生かそうとする「学びに向かう力、人間性など」 そして、これらの力を育むために、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点から、「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も重視して授業を改善することが要求されている。 (2)新共通テスト上記の学習指導要領の改訂を受けて、大学入試センターは、令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの問題作成の方向性として、
「大学で学修するために共通して必要となる、高等学校の段階において身に付けた基礎的な力を問う問題を作成する。 特に、新学習指導要領において、「主体的・対話的で深い学び」を通して育成することとされている、深い理解を伴った知識の質を問う問題や、知識や技能を活用し思考力・判断力・表現力等を発揮して解くことが求められる問題を重視する。その際、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を、教科横断的に育成することとされていることについても留意する。」 「例えば、社会や日常の中から課題を発見し解決方法を構想する場面、資料やデータ等を基に考察する場面、考察したことを整理して表現しようとする場面などを設定することによって、探究的に学んだり協働的に課題に取り組んだりする過程を、問題作成に効果的に取り入れる。」 (独立行政法人大学入試センター プレス発表資料より抜粋) と述べている。 今回行われた共通テストは、確かにこの方向性に沿ったものであり、様々な資料から必要な情報を的確に採取し、思考、判断していくことが要求される設問が多かった。 
2. 2025年の共通テスト2025年から大きな変更があるため、大学入試センターは2022年に試作問題を公表している。今回行われた実際のテストは、この試作問題とほぼ同じ傾向の問題であった。 (1)英語 全体として、様々なテクストから必要な情報を得たり、大意を把握したりする力などの速読即解力、情報処理能力が求められていることは昨年までと変わりがない。また、新課程で「表現する力」も求められていることを受けて、第4問と第8問が作問されている。 (2)国語 前回までは近代以降の文章が大問2問であったが、大問が一つ追加され、試験時間は80分から90分になった。追加された第3問は、試作問題の問題Bの形式に類似した問題であり、外来語の使用について複数の資料を読み取りレポートを推敲するという問題であった。「表現活動」に関わる出題であり、新課程にふさわしい問題であろう。 (3)数学IA 前回までは、数学A分野で「確率」「図形の性質」「整数」の3題から2題を選択する合計4題だったが、新課程で「整数」がなくなったため、合計4題全問必答となった。 (4)数学IIBC 前回までは、数学B の「統計的な推測」「ベクトル」「数列」の3題から2題選択で合計4題だったが、今回から数学B の「統計的な推測」「数列」、数学C の「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」の4題から3題選択、合計5題となった。1題増えたので、試験時間は60分から70分になった。 
(5)地歴公民 新課程において科目の再編が行われ、「歴史総合」という科目が必履修科目となっている。この科目は、「近現代の歴史の変化に関わる諸事象について、世界とその中における日本を広く相互的な視野から捉え、資料を活用しながら歴史の学び方を習得し、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察、構想する科目」(高等学校学習指導要領より抜粋)であり、日本史と世界史の両方の内容を含む。 (6)理科 受験科目の再編は行われたが、内容面では大きな変更はなかった。 (7)情報I 学習指導要領の変更に伴い共通テストに「情報I」という教科が新設された。ほぼすべての国立大学では、文系理系を問わず、受験生に原則としてこれまでの5教科7科目に「情報I」を必修として加えた6教科8科目を課している。
・情報社会の問題解決
試作問題は、この全範囲から出題されていたが、今回の共通テストも全範囲から満遍なく出題されていた。知識は教科書で十分だろうと思われるが、すばやく問題を理解し、知識を活用して問題を解決する思考力が必要とされる問題であった。今回は初回であって、問題としては難しいものではなかったが、次回からはもう少し難度が上がる可能性はあるだろう。
・コミュニケーションと情報デザイン ・コンピューターとプログラミング ・情報通信ネットワークとデータの活用 
3.おわりに 近年、情報化・グローバル化の加速度的進展やAI の飛躍的発達による技術革新により激しい変化が起きており、今後も社会の変化はさらに進むと考えられる。このように社会の変化が激しく、未来の予測が困難な時代の中で、子供たちには、変化を前向きに受け止め、より良い社会の創り手になっていくことが期待される。社会の変化に対応し、生き抜くために必要な資質・能力を備えた子供たちを育むことが大切なのである。
|
| ≫PAGETOP |