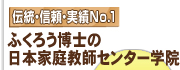開催500回を超える研修会
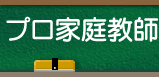 |
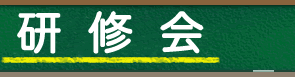 |
 |
 |
平成31年2月10日、父、義男が他界した。 今回は、学院長のご厚意により、父の追悼を兼ねての講演を許可いただいたので、父のライフワーク「採話」について述べる。以下は父が平成30年10月13日、桐生倶楽部で行った講演内容に「民話採録50年のあゆみ」より引用した。 「採録」とは、記録、録音、録画等することである。「研究家」は物事をよく調べ、真理を明らかにすることを生業とする。「伝承者(語り部)」は、昔からの言い伝え、風習などを受け継いで、語り伝えてゆく人々である。 採集する話には、民話、昔話、俗信仰、世間話、伝説などがある。 民話とは、民衆の中から生まれた創作文学。事実や史実ではない。民話は、神話を除く昔話、俗信仰(迷信、禁忌、予兆、卜占、諺など)、風俗習慣、世間話、伝説などの総称である。(異説もある) これらの伝承を研究することで、生活、信仰、しつけ、郷土愛、願望などが想像できる。祖先からのすばらしい贈り物である。祖先の生活状況、芸能活動、創作能力などや、祖先の地域交流の様子が偲べる。 民話との出会いを果たしたのは、学校新聞の保存を願って、昭和36年(1961)から民話の採録、連載を始めたのがきっかけだ。子どもたちの作成活動そのものが教育の場(ニュースの価値判断力、取材力、表現力、文字の上達、創造力、レイアウト力、共働、協力、工夫、達成感などの向上、充実など)となった。 民話採録活動は、民話の採録活動自体が楽しみ(採録の瞬間の感激)であり採録地の歴史、地理、風習などの理解が進んだ。(青年団入会条件、嫁入り時の村道、村の催しなど)
◇民話紹介
群馬県桐生市梅田町四丁目の民話 カッパと石金老人と意気投合したカッパオチまでついた珍しい民話
今は、たくさんの家々が軒を並べ、どの町会もみんな同じような街並みになってしまいましたけれど、昔の梅田の人たちは、当時、特に家数が多く活気のあった四丁目の「上の原(かみのはら)」を『梅田の銀座』と呼んでいました。
その「上の原」の東の端を静かなせせらぎとなって、流れて下っていく桐生川の中に、「釜ヶ渕(かまがふち)」と呼ばれる渕があります。今でこそ釜ヶ渕に近づく人の影は見られなくなりましたが、昔は子供たちの遊び場として、なかなか人気のあったところでした。 でも、とっても深い渦の巻く渕でしたので、子供を持つ親たちは、子供たちが水難に遭って恐れて、釜ヶ渕へ近づくことをきつく戒めていました。 現在の渕はすっかり浅くなって、怖ささえどこかへ行ってしまいましたが、 「明治の初めのころはな、釜ヶ渕は底知れねえ深え渕で、水が青くよどんでいて、見るからにカッパなんどが出てきそうでなーそんな感じのするところだったよ。」 と、近所のお年寄りが話されるように、怖さもいっぱい漂わせていた渕でした。 実は、その釜ヶ渕にとっても楽しい「カッパの民話」が残されていました。 むかァしのこと、上の原に鳳林寺(ほうりんじ)(糸井俊一さん宅)の分家で、清水屋という屋号の店がありました。その清水屋さんに、慈悲深いことで知られるおじいさんがおりました。おじいさんは、もう隠居身分でした。ですから、店の仕事には手を出す必要はありませんでしたので、お天気のよい静かな日には、釜ヶ渕近くにある畑にでかけては、そこで野菜づくりを楽しんでました。 ある年のこと、おじいさんが例のように、その畑にキュウリをつくったところ、その年は、良い天気が続いた上にほどよいお湿りがあったこともあってか、できのよいキュウリがたくさんとれました。 そのみごとなキュウリを見たお百姓さんたちが、 「このキュウリは、本当にじいさんがつくったのかい?あんまり見事なできなんで、おらぁ、もう、ぶったまげたよ。」 「これからキュウリつくりは、じいさんに手ほどきしてもらわにゃなんねえな。」 などと、冗談を言うほど、ほんとうにびっくりするほど立派なできのキュウリでした。 おじいさんの畑の近くに、釜ヶ渕という名の深い渕がありました。昔から「釜が渕にはカッパが住んでいる。」と言われているところでした。その釜が渕から一匹のカッパがニョッキリと顔を出して、物欲しそうにキュウリを見つめるようになったのは、そんなころからでした。 おじいさんは、そんなカッパの姿をめざとく目にしました。もともと慈悲深いおじいさんでしたから、キュウリを見つめるカッパの様子を見ると、もう黙ってはいられません。 「お前、このキュウリが欲しいんかね。欲しけりゃやるよ。遠慮なんかいらないから、ここへきて好きなだけもいで食べなよ。」 と、カッパに言葉をかけてやりました。 この言葉に、カッパはうれしそうにニコッと笑みを浮かべると、すぐさま渕からはい上がって、チョコチョコと畑にやってきました。そして、おじいさんの顔を横目でチラッ、チラッと見やりながら、一本のキュウリをもぎとり、とってもうまそうに食べました。 そんなことがキッカケとなって、カッパは、おじいさんが畑にやってくるたびに、渕からはいだしてきては、キュウリをもいで食べるようになりました。そして、いつしか、食べ終わると近くでのんびり遊ぶほど、とってもおじいさんになついてしまいました。 ある日のことでした。おじいさんが、すっかり伸びてしまった畑の草むしりを、一生懸命にやっているときでした。カッパがソーッと後ろから近づいてきて、やにわにおじいさんの股ぐらへ手をさし入れたのです。しかも、なんと、おじいさんのあの大事なモノをさわり始めたのです。 「おじいさんよ。これ、なんだい?とってもあったかくって、やわらかいものがあるよ。」 おじいさんが、おもちゃされてくすぐったいのをがまんしながら、 「それはな、おじいさんの大事なもんで、キンというんだよ。」 と答えると、カッパは、 「フーン。キンておもしろいんだね。」 といって、なおもさわり続けました。 そのうちに、 「キンだ、キンだ、キンだぁ。」 と、大声をだしてはしゃぐ始末でした。 いくら人のいいおじいさんでも、大事な「キン」をそんなにいつまでもさわり続けられたので、たまったものではありません。 「これはたまらん。あしたからは、なんとかせにゃなんねなぁ。」 と、翌日からは、ふんどしのなかに小石を包んだ袋を入れて、それをわざとブラブラさせてみることにしました。 次の日の朝のことでした。おじいさんが昨日に続いて草むしりを始めますと、渕からカッパがノコノコと出てきて、またまた同じように、おじいさんの股ぐらに手を入れて来ました。けれど、キンの手触りが昨日とはだいぶ違いましたから。 「あれえ、へんだなあ?今日のキンは昨日のキンとは違うぞ。なんだかとっても固いな。そうか、こりゃあ石金(いしきん)と言うんかもしれないぞ。そうだ石金だ!石金だ、石金だぁ。」 と、かえって喜んで、昨日以上にたわむれ続けました。 そんな無邪気なカッパでしたから、おじいさんも、いつしかカッパを孫のようにかわいがるようになりました。 ですから、しまいにはカッパのほうから、 「おじーちゃーん、いる?」 といって、清水屋さんの店先にまで遊びにくるようになりました。 おじいさんとカッパのへんちくりんな関係の日々が過ぎて、やがて夏も終わり秋となりました。その秋もだいぶ深まったころのことでした。店先の縁台に腰を下ろして、一人で遊んでいたカッパが、何を思ったのかツイッと立ち上がりました。 そして、 「おじいちゃん、長い間、オレをかわいがってくれてありがとう。畑のキュウリはうまかったよ。だからさ、今度はお返しにオレの宝物をおじいちゃんにあげるよね。」 といって、スタスタと釜ヶ渕の方へもどっていきました。 「カッパの奴、ワシにどんなものをくれるつもりなのかいな。」 おじいさんは、カッパがいい残していった言葉を楽しみに、カッパのもどってくるときをニコニコしながら店先で待っていました。 ところが、当のカッパはまるで鉄砲玉のお使い――渕へいったきり、待てど暮らせど、とんと清水屋へは戻ってきませんでした。 「カッパの奴め、いったいどこまで宝物を取りにいったんじゃろうなあ。」 待ちくたびれてしまったおじいさんは、両手を後ろ手に組んで店を出ると、トコトコと釜ヶ渕まで出かけ、渕をのぞきこんでみました。すると、渕のかたわらで汗びっしょりになったカッパが、七〜八寸(およそ23〜26cm)くらいの錦の巻物のような宝物を、はだか馬の背中に乗せようと、真剣に取り組んでいたのです。 でも、カッパがいくらがんばっても、なんとしても、はだか馬の背に宝物は乗せられません。乗せたとたんに、コロコロコロッ、コロコロコロッと転げ落ちてしまうのでした。 「ハッハッハ。カッパの奴め、困ってる、困ってる。ドーレ、ワシがちょっぴり手を貸してやることにするかな。」 おじいさんは、そうつぶやいて、口の前に両手でメガホンをつくると、渕のそばのカッパにむかって、 「オーイ、小僧、ワシがちょっくら助(す)けべぇかのぉ。」 と怒鳴りました。 突然の大声に、ビクッとしたカッパが、急に恥ずかしそうに顔を真っ赤に染めておじいさんのほうを見ると、何も言わず、「ドッポーン」と渕に飛び込んでしまったのです。その時以来、あんなにまつわりついていたカッパが、二度とおじいさんの前に姿を見せなくなってしまったのです。 釜が池のカッパ……今はどこに暮らしているのでしょうか。
「ふるさと桐生の民話」第2集 清水義男・編
2002年8月 日刊きりゅう 発行 より一部修正
この話のように、民話には物語としての体裁がない。カッパがなぜ石金を喜んだのか。なぜ、おじいさんにお礼の約束をしておきながら姿をくらましたのか。錦の巻物はどうなったのか。鶴の恩返しならぬカッパの恩返しはどうなったのか、など。 父はまとめとしてこう語る。 父は、熱心な研究者であった。ただ残念なのは、後継者を作らなかったということだ。何でもかんでも一人でやってしまう父であったため、逝くときは、すべて一人で抱えて他界した。「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」というが、父の残した業績が、何らかの形で後世に伝えられていくために何ができるのか。これが息子の私に残された課題であると思う。 |
| ≫PAGETOP |