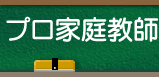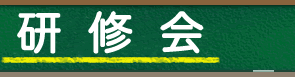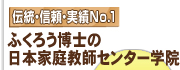|
師弟関係と言えば、歌舞伎が日本人にはなじみ深く、独特のものがある。
「大幹部」といわれるスター役者の家に限れば、そこに生まれた子は「御曹司」と呼ばれ、生まれた時から主役になる道が決まっており、よほどのことがないかぎり、主役になる。
最近だと、7月歌舞伎で海老蔵と息子の勸玄君が父子共演を果たし、人気を博した。この二人の場合、父の海老蔵が先生で息子が弟子、という子弟関係となる。ところが、海老蔵の父・団十郎は4年前に亡くなっている。では、誰が今、彼に芸を教えているのか。
歌舞伎には「お弟子さん」と呼ばれる人が、それぞれの家にいる。市川家で言えば、十二代団十郎の弟子だった人たちだ。厳しい主従関係であり、弟子とは言っても、師は彼らに何かを教えるわけではない。弟子は見て覚えるしかない。さらに、弟子がいくら「勧進帳」や「助六」を見て覚えたとしても、彼らが歌舞伎座で助六を演じることは絶対にない。では、彼ら弟子たちは何のために習うかというと、海老蔵に教えるためである。いまの海老蔵の弟子たちは、将来、勸玄君に教えるために、海老蔵の藝を頭に入れる。 「お弟子さん」は藝の継承を担う人たちなのだ。
御曹司と呼ばれる人は皆生意気であり、はるか年上の、たとえ70代のベテランでも、ため口をきく。敬語を使ったのでは秩序が成り立たない、一般世間とはかけ離れた世界と言える。
さて、西洋音楽が日本に輸入されて150年近くが過ぎているが、日本の音楽教育はいびつでゆがんだ展開をみせた。
本来合理的であったはずの西洋音楽が、日本に輸入されると、家元制度として発展した。
東京芸術大学は最高の権威だが、今もって完全に徒弟制度になっている。受験するには、芸大の教授の個人レッスンを受けないと受からない。一生その先生との子弟関係が続いていき、決して先生より偉くなってはいけない。叛旗を翻す才能ある若者は、芸大や日本の音大に行かずに、あるいは出た後で外国の音楽院に入り、活躍していく。
そうすると、もう日本の音楽の世界には戻れない。東京芸大の教授は就職の斡旋をしてくれる。その音楽システムに入り込めば安泰だが、芸大からは世界的演奏家は生まれない。
では、本来のお手本であったはずの、ヨーロッパの音楽教育はどういうものだったか、その歴史を繙いていきたい。
クラシックは17世紀初め、イタリアが発祥の地。ローマ教会がルーツである。口伝だと劣化コピーの状態になるのを防ぐため、楽譜が生まれ、それを利用し娯楽としてのオペラが生まれた。教会音楽とオペラが西洋音楽のルーツだ。
今は、音楽家は有名になれば収入もステイタスもあり、憧れの職業だが、昔は社会的身分も低かった。バロック時代、バッハやヘンデルといった音楽史に燦然と輝く偉大な音楽家が生まれたが、バッハですら、「芸術家」という地位ではなく、「使用人」、雇われサラリーマンであった。
音楽家はめざすものではなく、親が音楽家だと子供もそうなるしかなかったという、いわば賤業であった。歌舞伎役者もその点では同じで、士農工商にも属さない。俳優の俳は人でないと書く。それだけ、特別な才能を持った人という意味もあろうが。
当時は、音楽学校も普通に誰もが入れる学校もなく、バッハは親から習っていた。何十人も音楽家の家系というのは、別段珍しくもない。
音楽家以外の職業だったのに音楽家になった人は、何かに失敗してその街、あるいはその国にいられなくなって流れ着いたような人。そんな一人が、モーツアルトの父・レオポルド。彼は才能があったのでザルツブルクの宮廷楽団で出世し、息子が生まれると、音楽を叩き込んで、「神童」として売り出して儲けようとし、あわよくば自分も、ザルツブルクよりも大きな都市で出世しようとした。
ベートーベンもまた祖父の代から音楽家だ。親が子に教えるというのは、子どもの才能を見抜いて伸ばそうというよりは、子供で商売しようという側面も強かった。
18世紀は親子の師弟関係が専らだが、19世紀になると違ってくる。19世紀前半、世界音楽史上に残るロマン派の音楽家たちが、数年の間に集中して生まれる。
メンデルスゾーン(1809) ショパン・シューマン(1810) リスト(1811) ワーグナー・ヴェルディ(1813)。
彼らは、若い頃から知り合いで、一緒に演奏したり、別々の都市にいるときは、かなり頻繁に手紙をやりとりしていた。彼らの父は音楽家ではなく、自分たちで音楽の面白さに気づき、音楽を始めた。この時代はすでに、親から子ではなく、他人に教える音楽家というものが存在していたということだ。
彼らは、自分たちを偉大だと思い、なぜ自分たちが偉いかを伝えるため、前代の音楽家の継承者であるとアピールする必要があり、コンサートに昔の演奏家のものを載せた。それまでは、自分の楽曲を演奏する場だったが、演奏会は名曲を鑑賞する場であるという風に、価値観を変えた。それによって、彼らの存在が偉大なものとなり、音楽史に残っていった。
メロディを作るのは人に教わるというより才能だが、それだけでは音楽にならない。作曲家すなわちコンポーザーとは、建築家ともいう。メロディ一つ浮かんでも、どういう和声をつけるか、数学的要素や理論が必要。それには基礎は欠かせないが、基礎を超えると、先生から教わったことを否定した人の方が、名作曲家になっていく。
先生との対立の最初の世代が、ショパンであり、シューマンであった。ショパンは、師と対立し、ポーランドを出ていく。シューマンは、青年になってから音楽を始め、音楽家としては出遅れていた。先生の娘と恋に落ち、大恋愛の末反対されて裁判にまでなり、何年もかかって結婚を許される。クララ・シューマンである。独学をしたのが、ワーグナー、ヴェルディ、ベルリオーズ。大人になって独学を始めたので、楽器はたいしてできない。19世紀後半になり、教会で学んでいたのがブルックナー。
ここまでは、音楽学校との縁は深くない。では、音楽院はいつ頃生まれたか。
一番早いのは、パリ音楽院である。フランス革命以降、正式な国立音楽院となるが、ルイ14世がオペラ好きだったため、革命前から王宮に音楽家の養成のための機関があった。
パリ音楽院はリストの入学を拒否しており、学長が才能を妬んだためとも言われている。
ミラノ音楽院はヴェルディの入学を拒否したが、後にヴェルディが有名になってから、「ジュゼッペ・ヴェルディ音楽院」と冠する。
ミラノ、ワルシャワ、ウィーンの音楽院は、ショパンたちが生まれた頃できた。ロンドン、ベルリンがそれに続くが、イギリスは、お金はあるが偉大な音楽家はビートルズまで出ていない。20世紀になってエルガーやホルストがいるが、小粒である。ロシアのサンクトペテルブルグは田舎ながら、チャイコフスキー、ラフマニノフ、プロコフィエフと綺羅星のような逸材が出ている。東京芸大はその後、アメリカのジュリアード、カーチスは20世紀になってからである。
20世紀は演奏家の時代だ。音楽院に入る時点ですでに天才なのだから、そこで今さら基礎を教えてもしょうがない。日本は先生のコピーを作る徒弟制度だが、西洋の音楽システムでは、テクニックの伝授でも、先生の言うとおりにしなさいという人はいない。そこで積極的にものを教えるというのでもなく、では何をするかというと、悩みのあったときアドバイスをくれるのである。
次に、『現代の演奏家50 』より、演奏家がどういう人とどんな出会いをして、どんな影響があったかというエピソードを抜粋して紹介していく。
小澤征爾は、日本を脱出し、留学先もなければ仕事もないのにパリに行く。そこで、シャルル・ミュンシュ、カラヤン、バーンスタインと、世界のオザワになるのに実に幸運な出会いがあった。カラヤンとバーンスタインはライバル関係で、この2人と両方ともに仲のいい人はめったにいない。それだけ、小澤は愛すべき人柄、悪く言えば八方美人ということであろう。
アンドレ・プレヴィンは今80過ぎだが、映画音楽も作り、一時ミア・ファローと結婚。ハリウッドで名声は得たが、どうしても指揮者になりたいと、サンフランシスコでアシスタント中、バーンスタインのリハーサルを見学した。その数日後にピエール・モントゥーの前で指揮をしたとき、その影響を受けたことをモントゥーは瞬時に見抜いた。見ただけで何一つ教わらなくても、瞬時にやってみたり、また別の指揮者がそれを見抜けたりというのも、天才同士の所以である。
クリスティという人はバロックが専門で、バーンスタインとは似ても似つかぬ音楽をする。彼もバーンスタインの指揮を見て、具体的なフレーズではなく、どうオーケストラに向き合えばいいかを教わったという。バーンスタイン自身は、「僕の音楽を好きな人はみんな僕の弟子だよ」と懐の深いことを言っている。
カラヤンの影響を受けたというエピソードはあまりないが、彼は私財を投じカラヤン指揮者コンクールを主宰し、何人かの才能を見出した。指揮者ではないが、3大テノールや秘蔵っ子と言われたアンネ・ゾフィー・ムターもカラヤンが共演し、ブレイクした。
カラヤンは35年間ベルリンフィルの首席指揮者・音楽監督を務めるが、後年オケと険悪になり、ベルリンフィルが出演を拒否。代わりにウィーンフィルに要請し、そこにムターが客演、かつての恩を返すといった逸話もある。
ミケランジェリは、生涯で演奏したよりキャンセルした回数の方が多い、めったに演奏しないピアニストだ。何かが気に入らないとやめてしまう、スリリングな奇行の人。ポリーニとアルゲリッチの先生であることでも知られる。
二人は2年くらい、ミケランジェリと師弟関係を結び別荘で暮らしたが、その間にレッスンは4回だけ。では、何を教えたかというと、沈黙すること。2年間は自分を見つめ直すために必要な期間であり、沈黙する勇気を教えてくれたのがミケランジェリだと、アルゲリッチは語っている。その教えで、彼女もキャンセルが多い。
ホロヴィッツも12年ステージに出ない時があった。ワイセンベルクは10年。沈黙は、大ピアニストには重要なことのようだ。
グリモーは若いフランスのピアニストで、音楽院を途中でやめ、反骨心のある人。指揮者のバレンボイムに練習させられ、疲れるだけなのでそれよりいい音楽を聴きに行きますと言って、アルゲリッチのコンサートに行き、それがまた良かったとも言ってのける。アルゲリッチとはその後仲良くなり、姉妹のような関係を作っていく。
先のムターとカラヤンのケースもそうだが、若い演奏家が偉くなり、後に先生を助けることもある。ギレリスはロシアの演奏家だが、先生は偉い人だったが、その先生がスターリン時代スターリンににらまれ、演奏できなくなった。ギレリスは、たまたまスターリンの前で演奏する機会があった際、演奏を褒められ、望みがあるかと言われ、先生を助けてほしいと直訴した。スターリン時代にスターリンに向かってそういうことを言えるだけでも、大変に勇気あること。下手したら、シベリア送りになる。そういった状況で、師を助けるという美しい師弟愛もある。
クラシック音楽の世界では、ここでどの音を出してというテクニックを教えるだけでなく、人間関係というものが音楽史の中にはかなり出てくる。今回は、影響を及ぼしあった音楽家たちや師弟関係について特に掘り下げてみた。
興味を持たれた方は、冒頭に紹介した拙著でより深く知っていただけたら幸いである。
|