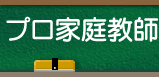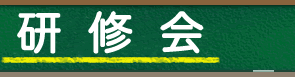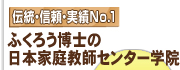脚本家って、どんな仕事? どうやってなったの? とよく聞かれるが、これといって道があるわけではない。私の場合は、大学を卒業し、就職し、それからやっと書き始めるという、スロースターターだった。
青山にあるシナリオ・センターに通う。そこで、ト書きは3文字空ける、時間が進むことを例えば煙草の長さで表すなど、シナリオ独特の文法を学ぶ。文法は教わるが、アイデアは教われない。悲しい顔、寂しそうに、といった演出家が戸惑う表現はNG。ポケットに手を突っ込み、うつむき加減で歩く、など具体的に指定するといった技術を学ぶ。
腕試しに、コンクールへの応募がある。昨今TV局のドラマも厳しく、コンクール自体下火になっているが、それでも今でも賞金800万クラスや、NHKでオンエアされるなどの特典があった。城戸賞などを目指して、30題お題を与えられ(「男と女」とか「裏切り」とか)、それで10分位のシナリオを書いては実力をつけていく。毎週書けば、30週で終わる。
大賞をとるとご褒美にオンエアしてもらえるが、城戸賞は、受賞という名誉だけで映像化はされない。映画化には莫大なコストがかかるからだ。
大抵は、局がワークショップを開催し、最終選考に残った人や次点位の人を呼んで、脚本家の卵を育てる。私の場合、フジのプロデューサーがたまたま若いチャレンジャーな方で、月9デビューとなった。初受賞でNHK放映された「おシャシャのシャン!」から、フジまでが長かった。
受賞はしたけれど、その後どう仕事につなげるか。最初は脚本ではなくプロット書きで、自分の言葉や思惑と違う方向へ行くことも多い。それでもくさらずに、書き続けていると、いずれ仕事につながる。
今はまず企画ありきで、持ち込みではなく、押さえてある企画で、枠がある。半年前(3期前)ぐらいに話が来て、秋から始め、春にオンエアという具合だ。
直していくときりがなく、それでか、初稿をぎりぎりまで出さない先生もいる。10稿位書き直すと、登場人物が変化したり、主人公の出生地が変わったりと、ボツ稿が増える。
「ちゅらさん」のライターさんは、“士農工商シナリオライター”と言いえて妙のことを言っておられた。身分的には一番下の下ということだ。
決定稿まで出すと、脚本家としての仕事はほぼ終わり、後は現場での仕事となる。現場は、脚本が別物として動いている。NHKとWOWOWは、脚本が決まってから撮り始めることが多い。映画の場合は、脚本ができてから、企画会議で通すか決める。演劇は、稽古が長く、稽古しながらどんどん変わる。
脚本家は、常に人と関わる仕事だ。ものを書くのが好きだからといって脚本家になっても、人と関わらず引きこもっていることはできない。「このセリフいらないでしょ」「いや、いります」といった格闘が常にあるのが脚本家で、自分の世界を完結できる、出来上がった世界に100%自己を投影したいなら、むしろ小説家を目指すべきである。
脚本家は、作品の土台を作るだけで、完成品ではない。芸術作品でもアートでもなく、注文品。そういう意味では、職人に近い。Aを書いてと頼まれ、Bではだめ。A+くらいにしといた、という程度のさじ加減が求められる。
脚本というのは、人とのつながりでくる仕事である。
NHK「おシャシャのシャン!」をたった1回見てくれた高畑勲監督から、いきなり電話がかかってきて、ジブリ「かぐや姫の物語」の共同脚本の話が決まった。
前作「いとの森の家」は、樹木希林さんの名演技が高い評価を得た作品である。おハルさんが、死刑囚を訪ね歩いていく。いかにも、昔何かあったんじゃないかという、いわくありげな雰囲気。おハルさんの告白のシーン。自身の贖罪の意味もあって、と事実が明かされる。
この時のセリフが、まるで自分が書いた言葉じゃないみたいに、樹木希林さんによっておハルさんの人生そのものの言葉になっているという、鳥肌が立つ程のすごい体験をした。
台本だけでは想像もつかない世界が、監督、演出家、役者さん、美術や技術スタッフ等の共同作業で出現する。
今、テトラクロマットという演劇集団で脚本を担当している。初演は「銀河鉄道の夜」をモチーフにした舞台。カンパネルラが、ザネリを助けようと池に落ちた。ジョバンニが、その手を離したことを後悔して引きこもっている。そうじゃない、俺が手を離したと言われ、救われる。手が離れ、水底に引きずられるのを、舞台でどう表現するか。
人形を出す、という舞台の記号を、お客さんと共有する。音響や照明でなんとなく水中なんだよということを表す。心に引っかかっていたことを思い出して、安心して眠ってしまうトキを、カンちゃんがなんとか銀河鉄道から降ろそうとする。思い出は大事だが、現実に生きよというメッセージ。小さな集団で最小限の装置でも、だからこそできる表現がある。
脚本家をやっていてよかったと思うことは、カンちゃんや、トキが、いると思って書くと、それが出てきて実際に動き出す。魔法のような快感を覚えると、やめられない。
シナリオ・センターの所長が、子供にシナリオを教えている、それで発見が多々あるという。
ドラマとは、葛藤と対立である。喧嘩がないと話は成立しない。違う意見もあることを知り、両方の見方ができないと、脚本は書けない。そこで、自分と違う意見に考えが及ぶようになる。
仕事として、自分たちは何とも思わずにやっているが、子供の中には葛藤や衝突、そして調和を図る知恵も自然に備わっている。書くことが、想像力や創造性のみならず、人との親和力を育てるのにつながることもまた、脚本・ドラマの持つ本来的な魅力ではなかろうか。 |