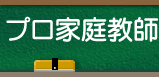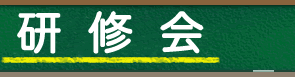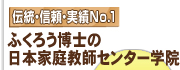教職を志した学生時代、様々な教育思想に影響を受けた。
ルソーの「エミール」は絶対的権威への反逆であり、学校および教育そのものへのアンチテーゼだ。自然のままの本性を善きものとみて、「人間は教育すればするほど歪(ひず)みが出て、悪くなる」とする主張は、教鞭をとる者としては肯(がえん)ずることはできないまでも、常に立ち返るべき挑発性を孕んでいる。
エレン・ケイの「母性」的愛情を主眼とする幼児、初等教育。生まれて間もない子供は、無条件に守ってやらねばならぬ存在であり、母親の無償の愛を超える教えはないということ。
法科大学院の受験指導をした時に、読んでいて思わず嗚咽が込み上げてきそうになった問題があった。インドのニューデリーの高層マンションが大火災に見舞われた際、若い母親が2歳の子供を抱いて17階の窓から飛び降り、自分は即死したが、子供は母親の体がクッションになり、奇跡的に無傷で助かった。一方、わが国でも若年層の出産率が増加し、育児ノイローゼに罹ったり、中には望まない出産の挙句、新しい別の男性に嫌われまいという理由から、子供を虐待し死なせてしまう母親もいたりする。「上記2例の母親のそれぞれのケースについて、違いを論ぜよ」という問題であった。
違いすぎるのは明らかで、「法学的視点から論ぜよ」ということなのだが、ここで社会的事象として見た場合にもすぐに気付くのは、父親の不在である。万一の場合に自分と子供を抱いて、飛び降りて死んでくれる巨漢の旦那でもいれば話は別だろうが、大抵男というのは肝腎な時に傍にいないものである。
心理学用語で、「老賢人」と言えば一段高みに立った位置から、俯瞰的に包容する「父性」的在り方のことだが、現実に子育ての場でも、受験・教育の場でも、忙しすぎる父親の不在が、母親に過大な精神的負担を強いている。状況さえ揃えば、私も前者の母親と同じことをしたかも知れないし、或いは後者の母親であったかも知れない。誰でも前者の母親になり得るし、後者の母親にもなり得る。
子供の成長過程には、母性と父性のバランスある関わりが望ましいが、一方を欠いた場合は一人が両役を負うという、過酷なロールプレイに立たされるのが現実である。
大学院時代、日本シュタイナーシューレ設立の歩みに関わった。シュタイナーの思想は、芸術を核とする〈自由への教育〉である。高校・大学と、常に「自由とは何か」というアプリオリな問いに、厳しく対峙することを迫られる環境にいた。そこで得た結論は、「教育とは自立した人間に育て上げることであり、表現活動そのものだ」ということに尽きよう。
新卒当時、私立高校で教える傍ら、都の農芸高校で特任講師として勤務した。正規採用には漏れたものの、シュタイナー教育が可能な場として、そのために自分が選ばれたとしか思えないような学校だった。ある日教室に入ると、目の前の女生徒が膝の上に仔猫を抱いている。誰も違和感なく溶け込んでいて、驚くのが逆に不自然な気もしたが、一応どうしたのか訊いてみる。親猫が死んでしまって、自分の両親も仕事でいないから、生まれたての仔猫は温め続けていないと、死んでしまうのだと言う。「死んじゃったら大変だから、しっかり放さないでいて、じゃあ耳だけこっち向けてね」・・・今思うに、「学校に猫なんて連れてきちゃだめよ」と言わない教師だったから、未熟ながらもなんとかやっていけたのではなかったか。
広い校内に鶏や牛がいて、産みたての卵で作った特製のプリンや豆腐を、生徒が誇らしげに届けてくれた。難しい言葉なんか何一つ使わず、黒板一杯に絵を描いて、窓の外を眺めて「桜がきれいだね。お弁当もって、外出たいね」と和み合ったひととき。生徒が皆優しく、毎日が楽しくて、あれが私の教育の原点であった。
オランダは、子供の幸せ度が世界一高い国である。その秘密は、教育にある。学校では、日本のような教師主導の一斉型とは趣を異にし、グループごとに机を寄せて、子供が主体的に学んでいく。各々が得意な学科で先生役になり、お互いに教え合う。それぞれが、交代で友達に尊敬心や思いやりを持ち合うのだ。
競争原理と経済効率優先の行き方は、右上がりに発展していく時代には適っていたかもしれないが、本来的に人間を育てるのが深い学びの場であるとしたなら、それには向かない。日本の子供は欲しいものが何でも手に入る〈豊饒〉の中にいて、それでも自分を幸せだと感じる満足度が世界的にみてかなり低いという現実を、我々大人は骨身にしみて考えていく必要があるだろう。
学力の到達度に世界中の関心が注がれる中、フィンランドの教育水準の高さが今、注目を集めている。リテラシーとは読み書き能力を指すが、言語的リテラシーのみならず数学的リテラシーにおいても、フィンランドの子供たちの学力は、世界的に群を抜いている。
理由は何か。夜が長い時間を活用して、大人も子供も挙(こぞ)って「読書」をするのである。親が読むから、子供も自然と読む。学校も読書を奨励するが、日本のように感想文のお仕着せなどで余計に本嫌いを助長させるようなことはしない。移動図書館の充実など、国を挙げての支援システムも整っている。
活字に渇えて、一食抜いても本を貪り読んだ時代は去り、生活の中にあらゆる情報や娯楽が満ち溢れている。授業の中で最新の情報機器を使う試みも、今後ますます採り入れられていくだろう。時代の趨勢には抗えないとしても、そうしたメディア教育が却って「読む力」としての国語教育を衰退させることになりはしないか、と一抹の不安を感じている。
限られた経験世界の中で見聞できることはごくわずかであり、本は悠久の彼方まで跳び越えて、未だ見ぬ〈世界・知らない誰か〉への「共感」を誘(いざな)う。
読解や論文指導の中で、「行間を読む」能力は、自己表現に至る前に必須のものである。他者の痛みや世界の事象を対岸のこととせず、「想像力」を喚起させるには、感受性だけでなく、「読む」という行為をどれほど切実に深くもったかにかかっているのだ。
本当には、自分が直接思い知らなければわからないのかも知れないが、若い人、とりわけ子供は、つらい不幸なことなどできるだけ知らないに越したことはない。年をとればだんだんつらいことが多くなり、その中で新しい世代が育っていくことが、せめてもの救いだからだ。親は重々それを知っているからこそ、少しでも楽ないい人生を送らせたいと、我が子を受験戦争に駆り立て、そのサポートに心を砕くのであろう。
今、毎日が真剣勝負の受験現場に身を置き、来る日も来る日も生徒の現実の苦悩や向上心と向き合っている。私のもてるものを出し切って、合格に導くことの醍醐味は、受験知識を超えた先の、学問や人生のとば口に彼らをいずれ立たすことにある。
日本語が滅びないために、本がこの先も愛されていくために、出会った教え子一人一人に、〈言霊〉の力を伝え続けていくことを使命としたい。
|