|
4月より、朝日新聞「キャンベルの苦楽考」の連載の中で、日本人が江戸時代から明治・大正・昭和にかけてどんなことを苦楽とし、幸せと考えてきたかを考察している。
幸福を、人生の節目でどう表現せずにいられないか。その根本は、「学ぶ」ことである。
書斎もしくは自分の部屋や研究室で、一人閉じこもって何かを学ぶのではなく、友と一緒に「遊ぶ」あるいは「学ぶ」―――「遊学」=「旅をする」ということは、普遍的に若い人達の一番の憧れであり、生きる手応え、自分の人生を表現するきっかけとなった。
「江戸時代の学びの風景」を見ていきながら、当時の書生が学ぶことによってどのように自己や人生を実現していったかを考えたい。
NHK教育「Jブンガク」でも採り上げた久米正雄「受験生の手記」(大7)には、一高受験に失敗し浪人、弟へのコンプレックスと失意から入水自殺する青年の話が出てくる。
私の勤務する東大の現役生に接しても、その学ぶ意欲に圧倒されると同時に、彼らが少年少女・青年時代に何を犠牲にし、あるいは妥協しながら生きてきたか、これからどう人生を完成させていくかということに、教師として思いを致さずにはおれない。
江戸の学び方は近代以降とはかなり違っている。江戸や明治前半には、競争システムは存在しない。試験に受かることによって、立身出世できるということではない。
一人一人の学ぶ姿勢が何を意味するかは、彼らが降り立った地平を見ていかないとわからない。
『古典日本語の世界』にみられるように、吉宗の時代から学問をある社会に限定して一部の専有物にするのでなく、広く一般の人々に学問を普及さすことによって、社会を繁栄させることができるという思想が浸透した。それぞれの各藩で三百数十の藩校が作られ、寺子屋が奨励される。識字能力も、ヨーロッパ先進国と並ぶ高さに達成をみた。
幕府が設置した昌平坂学問所も、最初は旗本の上層部のものだったが、後には全国の諸藩の有望な学生を募り、勉強させる寮を開放。儒学の中でも、朱子学がオフィシャルな学問として奨励され、封建倫理を支えた。
 寛永年間に異学が禁じられていた時期があったが、張本人の松平定信ですら後々「学問の流儀は何にてもよろしき候」と異学を認めている。 寛永年間に異学が禁じられていた時期があったが、張本人の松平定信ですら後々「学問の流儀は何にてもよろしき候」と異学を認めている。
他流試合をし、学問を競わせることで活性化する。勢い寮には「素読」ができる、四書五経の白文ぐらいは読みこなす学力をもった者が集まってくる。
「師とする所は書籍と朋友に在り、勤むる者は日に進み、惰(おこた)る者は放逸に流るるを免れず」[「昌平大学の総況」(高橋勝弘編『昌平遺響』)三近社]
別資料中「回評」とは、詩を作って仲間内で交換日記のように回し合う、書き込みの講評である。また、棒給が出る舎長・助勤よりも、「詩文掛」は学生の中から選ばれ、皆が憧れる職分だった。
日本社会は得てして年功序列だが、ここでは完全に成果主義である。努力すれば達成するというものではない。努力はもちろんだが才能がないといけないということを、皆わかっている。試験を突破するという誰が見ても納得する「数値」で測られる世界でなく、寮の中でつきあい修養する中で、仲良く自然な「関係」が浮かび上がってくる。いろいろなことを学び教え合って、知っていく。若い人の精神文化の在り方として、嬉しいと同時にどこかホッとする。

茲(ここ)に十代の初めから才能を嘱望され、詩友学会に推挙された中島子玉の書いた一文がある。
「蕉葉の上に書す」(芭蕉の葉の上に文字を書く)と題し、「夜、書き物をする時や書物を読みながら、芭蕉の木があれば風が吹いているのか雨なのかすぐわかる。」と、詩文中彼らが芭蕉の木を心の中の心象風景で、いかに愛し大事にしているかがわかる。
こうした文献からは、激動の最中に学問生活に満足して、充足している学生の姿が垣間見え、歴史に立ち会おうとする息吹が聴こえてくるようだ。
彼らは、幕府のお膝元にありながら、深いところで倒幕へのエナジーとなっていく。
近代以前の書生達が、何かを学んで学問的生活の中で、「個」として充足した自分の人生を切り拓く―その声を聴くことは、現代の教育や社会全般を考える上でも、有益である。 |
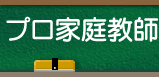
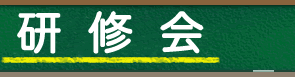



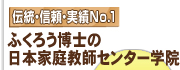



 寛永年間に異学が禁じられていた時期があったが、張本人の松平定信ですら後々「学問の流儀は何にてもよろしき候」と異学を認めている。
寛永年間に異学が禁じられていた時期があったが、張本人の松平定信ですら後々「学問の流儀は何にてもよろしき候」と異学を認めている。