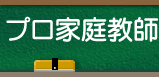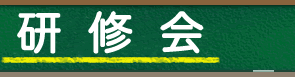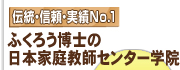|
 |
 |
 |
世田谷パブリックシアタープロデューサー。
劇団四季、こどもの城劇場事業本部(青山劇場・青山円形劇場)などを経て、96年、世田谷パブリックシアター開場準備室にスタッフとして参加。98年より現職。
ストリート・プレイ、音楽劇、ダンス、こどもの劇場(親子で楽しめる舞台企画)、ワークショップなど幅広い分野でプロデュースを手がける。
 |
|
演劇は、不可欠なものではない。劇場というのは、非日常空間で、リセットできる場である。だからこそ、我々はより多くの方に来ていただけるために、仕事をしている。
<演劇を創る仕事とは>
世田谷パブリックシアターは、日本初の発信型の公共劇場として、97年にスタートした。地域の公共活動に根差しつつ、地方にも発信していくというあり方で、これによって初めて演劇プロデューサーという仕事が確立した。
それ以前は、劇団がソフトを創る、劇場はハードにすぎず、いわば演出家が「神」だったが、もっと劇場が地域に根差してものを創るということをより自由にできたらということで、パブリックシアターが始まった。
実際に、企画を立て、出演者・スタッフを決め、予算を立てといった具合に、どんどん動いていく。今も公演中だが、目先のことをやりながら、来年・再来年の企画を立て、同時進行的に幾つものことが運んでいる。
商業演劇は、30分以上お弁当を食べる休憩の入るお芝居、「放浪記」のような誰もがわかりやすいものをいうが、その対極にあるのが、小劇場の小さな空間でこれからの若い人によって自作自演されるエネルギッシュなもの、こちらは観客も演じるほうも若い。
パブリックシアターはそのどちらでもなく、いわば日本演劇界のレパートリーとなるような、いつまでも人々に支持され愛され続けるような作品創造をめざしている。
変に前衛的なものでもなく、なぜ今これをやるのかということ。
「放浪記」はなぜ今ということではなく、やることに意義がある。森光子というアーティストがいて、彼女のためにある、お芝居をやることでビジネスになりうるし、観る人を選ばない。
既存の劇場とは一線を画するような、公共劇場でなければならないような作品を創っていかなければと思っている。劇場は、特徴を出さなければ生き残れない、存在価値がないものであろうから。
歴代の作品で、1万人お客様を呼んだ、白井晃演出による「偶然の音楽」というのがある。この時は、世田谷パブリックシアターでなければできない創作方法はないだろうかと考え、小説の戯曲化にあたって劇作家を介在させずに、「会話」の部分だけを演出家が構成し直して俳優に喋ってもらい、演出家と俳優だけで作品を創り上げた。
俳優の身体を通して、演劇的・立体的に気の遠くなる稽古をする。通常の舞台では4週間が相場だが、この時は8週間かけた。
演劇的な演出方法にもこだわって、特徴的なシーンの一つは、ポーカーをする場面を演出家がどう描いたか。
ごくごくシンプルに、トランプを人が持って出たり入ったりするという手法により、ポーカーの場面を表現するという、観客が想像力を活かすことができる演出で描いた。
<子供のための舞台作品>
これらの舞台は大人が鑑賞するものだが、もうひとつ私がライフワークにしているのが、子供のための作品である。
子供のものは、わからない作品は観てもらえない。今まで、「ピノキオ」「美女と野獣」など、子供にとっつきやすいものを題材に採っている。
子供はセリフではなく、目と耳で「音」や見たままを理解するので、セリフはポエティックな要素が多い。「だから…」「明日は…」などの具体的なセリフは少ない。
子供向けに作っているという意識はなく、子供こそごまかしがきかないものだから、子供も楽しめる大人劇を創っている。
童話の中でも実人生の上でも、少女が大人になっていく過程において、ある決断をする。それはまた、責任を伴い、痛みも伴うものだ。
たとえば「にんぎょひめ」のワン・シーンで、人魚姫が「人間」になるために魔女のところへ行く。最初衣裳を足に被っているが、すっぽり抜けて、赤い血糊が塗ってあって、歩くと「痛み」のために赤い足跡がつく。
大人になるとはそういうことで、完全にはわからなくとも、何かを感じ取ってくれればいい。この演出がなぜ子供向きかわからない、見せるべきではないと怒って帰る人もいるが、子供劇への固定観念は不必要と考えている。
子供が大人と対等になれる唯一の場所が劇場である。一緒に座って、時間や感動を共有できる。大人が面白かったねと言っても、子供が面白くないと言えば、それだっていい。
教育に携わる世界とは異業種だが、共通なのは人を相手にしている点である。
人が人と仕事をしている。演劇はすべて人である。
企画を立て、演出・美術、すべて大勢の人が集まって、人を動かして力を結集する。

魂を懸ける。気が入っていないと、その作品が歩いてくれない。
全力で考え続ける、思い続けることが必要。お祓いをしないと、怪我、トラブルが起こることもある不思議な空間ではある。
全身全霊で向き合っていると、自分の作品は我が子のような、愛おしい気持ちになる。
どこの劇場のプロデューサーも、魂を懸け本気で創っているので、機会があれば劇場に足を運んでそうした「気」を感じていただければ、感じさせたいなという気でやっている。
「劇団四季」にいた時、ものすごい数の観葉植物に水をやるのが、新人の仕事だった。厭になったことがあってサボってしまったら、枯れてものすごく怒られた。
今になって考えると、それが人に対しても気を遣うということ、植物も育てられない人間に芝居なんか創れるか!ということだと思う。何も言わない植物だからこそ、植物の気持ちになって先回りして考える。これと同様にスタッフや役者さんと接することが大切なのだと教えられた。信頼関係やコミュニケーションを築いていくには、相手の身になって物事を考えることが大切である。
大人になっていく子供の言葉には、寓意的な要素もまた読み取れる。
子供の作品をイタリア人の演出家と一緒に創った時に、「旅をする」ということがテーマとなった。
「雪の女王」で、少女カイがゲルダを探しに行く。旅に出る過程で、経験を積むことが成長につながる。
私もそうで、自分で物事を決め、次に進んでいく。そういう要素を、作品に込める。
「にんぎょひめ」のような悲しい結末であっても、自分で決めたことは「信じて進む」というメッセージである。
何かが起こって自分でアクションすることが、子供にとっては勇気が要る、経験を積んで大人に近づいていくことだと思っている。そこを表現し、作品を創っていきたい。
|