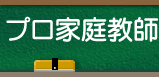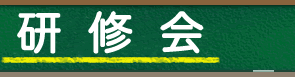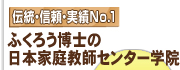|
 |
 |
 |
映画監督・脚本家。日本映画学校理事。 1959年東京生まれ。琉球大学法文学部卒業後、新潮社に入社。八年間編集者 として勤務の後、退社して映画監督となる。
●主な監督作品
『妹と油揚』 『アジアン・ビート/アイ・ラブ・ニッポン』 『無敵のハンディキャップ』 『AIKI』 『暗いところで待ち合わせ』 『世界で一番美しい夜』(2008年公開予定)
●主な脚本作品
映画版・濱マイクシリーズ三部作(林海象監督) 『うなぎ』(今村昌平監督) 『カンゾー先生』(今村昌平監督) 『赤い橋の下のぬるい水』(今村昌平監督) 『11’09”01セプテンバー11』(今村昌平監督)
『オーディション』(三池崇史監督) 『インプリント〜ぼっけぇ・きょうてぇ』(三池崇史監督)
 |
|
僕はプロの映画監督であり脚本家でもあるが、日本映画学校という、父・今村昌平が設営した専修学校に関わっている。どんな仕事にも教育効果があるように、映画を作る過程もまた人間が成長できる機会である。多くの学生は「映画が好きで、映画の世界に飛び込んでみたい」「映画界に直接いくのは怖いから、まず学校で基礎を学びたい」というような理由で受験してくる。我々は彼らに様々なことを教えている。
映画で一番重要なのは、言葉によるコミュニケーション(人に何かを伝える)ということだ。どんな映画も個人的なアイデアからスタートするが、一人では作れない。常時50人、多いときで100〜200人が動く。複数の人が集まって時間もお金もかけて作るとき、自分が何をすればいいのか理解するための方策は<言葉>である。
映画は監督に権限があり、全てを決めなければならない。スタッフに対してもキャストに対しても、相手がどんなコンディションなのかを冷静に見た上で、ナイーヴに判断を下すことが求められる。
演出で一番重要なのは俳優さん個人個人の持っている魅力を引き出すということだ。監督はどうやって相手の魅力を引き出すかということに腐心する。怒る、黙り込む、のべつまくなしに喋るなど様々な手管を使うが、それは人と人が接するとき(家庭教師が教えるとか相手に頼むとか、人を口説くとか)の延長と言えるだろう。
映画監督のできることは3つある。
1つは<手品>だ。
映画はトリックである。実際は人を殺してないのに殺しているように見せる。この部屋を3倍ないし100倍広く見せることもできる。伊丹十三監督は陽炎がゆれる映像を撮りたいとき、燃やした固形燃料をレンズの下に置いて撮った。一つ一つは大したことはないが、手品がわからないと映画は撮れない。
技術的なもの以外に人間の所作もある。コップで水を飲む際の男らしい表現、女性のしとやかな感じ。キスの仕方で二人の関係を表す。挨拶程度か情熱的なのか。
引出しが多ければいいというわけでもないが、ベーシックなものは覚えておくといい。手品はテクニックなので比較的勉強しやすい。
その先には <魔法>がある。
心の中は写らない。人間的な感情、哲学的な思索は写らない。外側にあるものを組み合わせて、内面をどう見せるか。手品が外側だとしたらこれは内側である。
コミュニケーション・信頼関係を基にして物理的でないものをどうやって引き出すか。どんな言葉をどんなトーンでどのぐらいの距離で伝えるか。相手を見て相手の気持ちを理解しながら、自分の思うように相手の魅力を引き出していく。これは、優秀な教師やカウンセラー、スポーツのコーチの言った言葉が、時として人生を左右することに近いと思う。
人間は常に揺れ動いている。体調・精神の状態は常に違う。流れているものは計算どおりにはいかない。本当にこうさせたいという思いがあるから伝わる。一番相手が反応する言葉が出てこないと魔法はかからない。トータルでその人を見て、相手が男だろうが女だろうが擬似的な恋愛状態に近いものができたとき、魔法はかかったも同然になる。
監督というのは、常に周りから値踏みされるものだ。自分にしかできないもの、自分ならではの表現を常に見せていかないと、人はついてこない。今まで見聞きしたパターンだけで無難にこなすのでなく、度肝を抜いてやる。そうすると魔法がかかりやすい。
手品・魔法の先には、さらに<奇跡>がある。
奇跡とは人間の力ではどうしようもないもの。コントロール不可能な天気やタイミングを、どうコントロールするか。まるでオカルトのようだが、経験的に、映画の現場では奇跡としか思われないことが起こりやすい。
まずスタッフやキャストの、レベルの高い集中力が必要だ。そして魔法が使える監督であること。知力・体力・精神力、あらゆる能力を振り絞り、<人事を尽くして天命を待つ>結果、奇跡が起こる。だから映画はやめられないのである。
映画の基礎は脚本だ。映画学校では、入学してすぐ脚本を書かせる。嘘をつきなさい、お話を作りなさいというストーリーテラーの教育は、日本の学校ではほとんどやっていない。
うちに来る学生の中には、劣等生・不良・引きこもりもかなりいる。引きこもっていた人が映画にいくというのは死にに行くようなもので、人生=未来を賭けて入学してくる。
文章なんか書いたことがなくても、面白いものを書けるヤツはいる。映画の学校は競争社会であり、早慶の文学部にいた者より、チンピラの高校生の書いたものの方が面白い場合もある。センスは教えられない。
しかし、センスだけでは限界がある。国語力というべきか、ちょっと歯応えがあり複雑になると、たくさん読んでたくさん書いている人間に敵わない。
脚本の構造というのは、数学に近い。論理的に考え、建造物を構築することに似ている。小説は枝葉があり、壁の色、快適さ、住居の肌合いなどを書き込むが、脚本は<骨組み>である。世の中のさまざまなことを、知らないと書けない。センスは絶対に必要だが、国語力、論理性、社会的なことへの知識や関心。それらが組み合わさらないと、大人が見て面白いものは書けない。基礎学力・教養というものは絶対に必要なのだ。
誰でも脚本家になれ、映画監督になれるものではない。歴史に残る監督になれる人間はそんなにはいない。いないのに、僕らは学校で教える。学校をさぼって映画ばっかり見てきた連中が最後の砦として、映画なら馬鹿にされない、見返してやれるとやってくる。
映画・芸能の世界は完全実力主義で、社会的マイノリティも平等に勝負できる。酷い目に遭ったり歪んでいたりする程、素質があるともいえる。生徒会長で、インターハイに出て東大を出てという人だったら、ギリギリの世界で勝負しなくても他で生きる余裕があり、だから生き残れないことも多い。
実学の世界では、下で行なわれていることの方が本当なのだ。
自分も、たくさんのことを映画から学んだ。
映画学校に入学した連中は、生まれてからこんな酷いこと言われたことないというぐらいのことを、毎日朝から晩まで僕らに言われ続け、変わっていく。成長していく。言葉のコミュニケーションを学び、論理的思考の必要性や社会への関心を持つことを学んでいく。きついけれど、映画が好きなら耐えられるはずだ。とどのつまりは、映画にプライドを持っているかどうかに懸かってくるものだと思う。
 |
|
最後に、映画は本来映画館で観るために作っているが、今はそうもいかない時代だ。新しい作品は当たり外れがある。それでも、新しさを楽しみたいなら、玉石混交を楽しむつもりで誰よりも先に映画館に行くといい。
生徒は、映画を観ている層が対象である。世代間の交流が少ないと、ある世代はあるものしか観ないということになる。若い人から発信されたものをキャッチしてみる。先生方からも発信して、大いに啓蒙してもらいたい。
そして、ちょっとはりこんでちょっと頑張って、一年に何回かは時間をみつけて映画館に行っていただけると嬉しい。
|
|