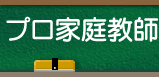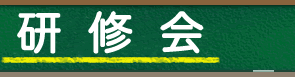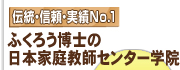|
 |
 |
 |
日本アドラー心理学会公認心理療法士。1941年東京生まれ。東京学芸大学卒。都立梅ヶ丘病院精神科心理主任技術員を経て、都立中部精神保健福祉センター勤務。その後、財団法人精神医学研究所兼務研究員、日本アドラー心理学会評議員などを歴任し、現在、子育てボランティア団体「わいわいギルド」代表のほか、IP心理教育研究所所長を務める。専門は個人カウンセリング、個人心理療法。著書に『アドラー博士が教えるこんなひと言で子どものやる気は育つ』(青春出版)『<困った大人>にしない子育て20の知恵』(金子書房)『アドラー博士の子どものピンチを見抜く法』(サンマーク出版)ほか多数。
 |
|
臨床心理学を専門にしている立場からみると、いい子の方がむしろ心配である。真面目に見えてすごくがんばっている子が、発達のある段階で突然キレテしまうということが、最近しばしば見受けられる。無理していい子を演じているようなのを「過剰適応症候群」というが、親や教師は見かけの「いい子」にまどわされないようにしたい。勉強にあきたとかもうしたくないと言う「困った子」の方が、実はこころの健康度は高い。
では、その見分け方だが、「自己肯定観」をもっている子、すなわち自分のことが好きな子ならば、まず心配ない。時間をかけて指導すれば、必ずゆっくり花開いていく。
治療現場では、有名校をドロップアウトし心の問題を抱えている子の方が、普通の学校の子に比べ、はるかに治しにくい。そういう子どもの共通項は勉強のみを得意としている子どもである。勉強だけで自分を支えてきた人は、一等賞がとれないと何も自信がなくなってしまう。そもそも、一生ずっと競争に勝ち続けるなどということは、できる訳ないのだ。
教育とはすぐに目先の結果が出るものではない。勉強ができることは素晴らしいことだが、勉強以外にできる何かを伸ばしていくことも、もっと大切だ。
では、子どものやる気を引き出すためには、具体的にどうしたらよいか。上手なコミュニケーション・スキルのとり方を3つ挙げてみよう。
- 理想の子どもではなく、目の前の子どもをしっかりと見る。
理想の子ども像が頭の中にあるとしても、「願い」にしておいて、目線を下げる。
「理想」―「現実」の引き算ではなく、「現実」にプラスして「理想」に近づけていく、スタートラインからの加算法でいく。
- 過去の自分と現在の自分という、子どもの中の個人内評価をする。
子どもがやる気を失うのは、自分が伸びているという実感が持てないときである。
先生の期待値にいったかどうかではなく、きれいな字がかけるようになったことでもいいし、前よりどれだけよくなったかを比較して認めほめる。
「人格」ではなく、「行動」を評価する。「やれるよ」「できるよ」ではなく、「やれたね」「できたね」という過去形の言葉かけがよい。
1回2回の結果ではなく、子どもの中で着実に伸びているという実感をほめ、小さなことでもいいから「やれた」「できた」ことへの達成感をもたせれば、積もり積もれば大きな自信につながる。
また、子どもを直接ほめるより、親に対して子どもをほめ、親から子どもをほめてもらう「間接話法」が効果的である。親にほめられるのが子どもは一番嬉しいので、いい気持ちになってやる気が増し、親子の関係もプラスになる。
- 「君はこうだね」という<断定>の YOU メッセージではなく、「先生はこう思うけど、どうかな?」というI メッセージにすると意見対意見の<話し合い>になる。
近年、青少年の大きな事件が起きる度に、背景や原因が取り沙汰されているが、生育条件などはあまり関係のないことであって、親が悪いとか環境が悪いとか言っても始まらない。「なぜ」ではなくて「どうしたら」を考えることのほうが重要である。
なぜ学校に行かないかではなく、どうしたらこの子が喜ぶか、何がこの子を集中させるかに心を配り、指導に当たられたい。
「学ぶ」とは、「真似る」からきているので、子どもが<同一視>をもって、「あの先生のようになりたい」と思える先生が、いい先生である。
尊敬に値する家庭教師になるには、
- 子どもの趣味を大切にし、得意なことを丁寧に聞いてやる。
- 子どもの予想外のことをする。
- 子どもの小さな変化をとりあげ、先生が自分に関心をもってみてくれていることをそれとなくわからせる。
子ども自身の成長を見つけてほめ、内発的動機づけを高めることこそが、子どもをやる気にさせる一番の方策である。
|